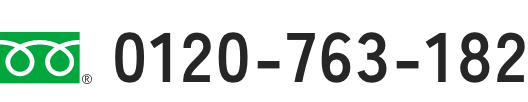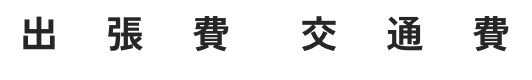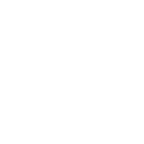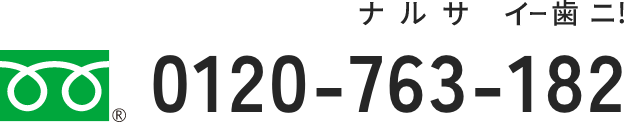歯ツラツくん
BLOG
「食べにくい」「むせる」が増えたら訪問歯科のタイミング?
「最近、母が食事のたびにむせるようになった」「以前より食べるのに時間がかかる」
——そんな変化を感じていませんか?
高齢のご家族様の食事の様子に変化が見られたとき、そこには口腔や嚥下の機能低下が隠れているかもしれません。
「食べにくい」「むせやすい」は、体のサイン。
そして、これらのサインが現れたときこそ、訪問歯科の出番です。
この記事では、そうした兆候がなぜ起こるのか、放っておくとどのようなリスクがあるのか、
そして訪問歯科では何ができるのかを詳しくご紹介いたします。
ご本人様が安全に食事を楽しめるように、早めの対応が大切です。
「食べにくい」「むせる」は何を意味している?
年齢とともに、咀嚼力や嚥下機能は徐々に衰えていきます。
「むせる」「飲み込みづらい」といったサインは、そうした身体機能の低下を知らせる重要な兆候です。
【主な原因】
・舌や頬、唇の筋力低下
・唾液の分泌量の減少
・歯や入れ歯の不具合
・誤嚥反射の鈍化
これらの原因により、食べ物をうまく噛めなかったり、口の中でまとめることが難しくなったりすることで、
飲み込む動作がスムーズにできなくなってしまいます。
また、加齢に伴う筋力低下だけでなく、脳梗塞の後遺症やパーキンソン病などの神経疾患も、
嚥下障害を引き起こす要因となることがあります。
【このまま放置すると…】
・食欲の低下 → 栄養不足
・脱水症状 → 体力低下
・誤嚥性肺炎 → 命に関わるリスク
誤嚥性肺炎は、食物や唾液、胃液などが気管に入ってしまい、その中の細菌が肺に感染することで発症します。
高齢者にとっては命に関わる深刻な疾患であり、早期発見や早期対応が求められます。
「最近むせることが増えたかも」と思ったら、まずは一度お口の状態を見直してみましょう。
ご家庭でできる初期対応
症状が軽い段階でも、日常生活の中でできる対策があります。
家庭内でできる簡単な工夫を続けることで、進行の予防や、日々の生活の質向上につながります。
1. 食事の環境を整える
食事中は、正しい姿勢を保つことが大切です。
椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、やや前かがみになる姿勢が望ましいです。
食事の際はテレビを消すなど、できるだけ集中できる環境を整えてください。
2. 食事の形態を見直す
「柔らかくて飲み込みやすい」「喉に引っかかりにくい」ことを意識して、食材を選びましょう。
例えば、きざみ食やペースト食、とろみをつけた飲み物などが適しています。
3. 食前の体操やマッサージ
食事の前に「ごっくん体操」や「パタカラ体操」などを取り入れると、口の筋肉や舌の動きがスムーズになります。
た、耳の下やあごの下を軽く指でマッサージする唾液腺マッサージは、唾液の分泌を促し、飲み込みやすさを助けてくれます。
4. お口の中の清掃を丁寧に
歯磨きや舌苔の除去をしっかり行うことで、口腔内の衛生環境を整えることができます。入れ歯をお使いの方は、毎食後の洗浄を習慣化しましょう。
訪問歯科の役割と対応内容
「一人で歯科医院に行くのが大変…」そんな方でも安心して受けられるのが訪問歯科です。
歯科医師や歯科衛生士がご自宅へ伺い、必要なケアを提供します。
【訪問歯科でできること】
・歯のチェックと治療
・入れ歯の修理・調整
・口腔清掃(歯垢・舌苔・粘膜)
・嚥下機能の簡易評価
・唾液腺マッサージやリハビリ
【保険適用で安心】
訪問歯科は、健康保険や介護保険の適用対象です。自己負担は1〜3割程度で、経済的にも継続しやすい仕組みになっています。
また、訪問エリアや対応可能な内容については、専門の窓口で相談することでスムーズに案内してもらえます。
ご家族様にできること
ご本人様が自覚していない場合や、伝えることが難しい場合でも、
ご家族様が気づいて行動を起こすことで、大きなサポートとなります。
1. 日々の観察と記録
むせやすさ、食事の時間、残食の量などを記録しておくと、医療機関へ相談する際に大変役立ちます。
日記形式で簡単にメモを取っておくだけでも十分です。
2. お声がけと心理的サポート
「最近、食べづらい?」などと優しく聞き、無理のない範囲で気持ちに寄り添う姿勢が大切です。
ご本人様のプライドを傷つけずにケアを進めるには、共感的な対応が鍵となります。
3. 安全な食事・生活環境の整備
食器の工夫、椅子の高さ、照明など、食事のしやすさを支える環境を整えていきましょう。
転倒防止や誤嚥防止の観点でも、生活空間の見直しは重要です。
4. 専門家への相談を促す
「お口の状態を一度見てもらおうか」「専門の先生が家に来てくれるから安心だよ」など、
前向きな提案で訪問歯科を勧めることが、ご本人様の安心にもつながります。
Q&A
Q:歯がない人でも訪問歯科を利用できますか?
A:はい。歯がない方でも、入れ歯の調整、舌や粘膜の清掃、嚥下リハビリなど多くの対応が可能です。
Q:「食べにくい」は老化だけの問題?
A:いいえ。病気や神経障害、入れ歯の不具合が隠れていることもあります。専門家による確認が必要です。
Q:訪問歯科の利用には紹介状が必要ですか?
A:基本的には不要です。訪問歯科専門の相談窓口やサービスに直接連絡することで、スムーズに予約が可能です。
Q:費用はどのくらい?
A:健康保険・介護保険が適用されれば、自己負担は1〜3割程度。1回あたり数千円で済むケースが多いです。
Q:定期的に来てもらえるの?
A:はい。お口の状態に応じて、週1〜月1回など、定期的な訪問スケジュールが組まれます。
まとめ
「食べにくい」「むせる」といった変化は、日常の小さな不調に見えますが、
実は重大な疾患や機能障害の入り口であることもあります。
ご本人様が自覚しづらいことも多いため、ご家族様の気づきが命を守る第一歩になります。
訪問歯科は、お一人で通院が難しい方でもご自宅で安心して受けられる医療サービスです。
専門的な視点から状態を評価し、個別に対応してもらえる点が大きなメリットです。
「どこに相談したらいいか分からない」「不安がある」という方は、弊社の電話相談受付へご連絡ください。